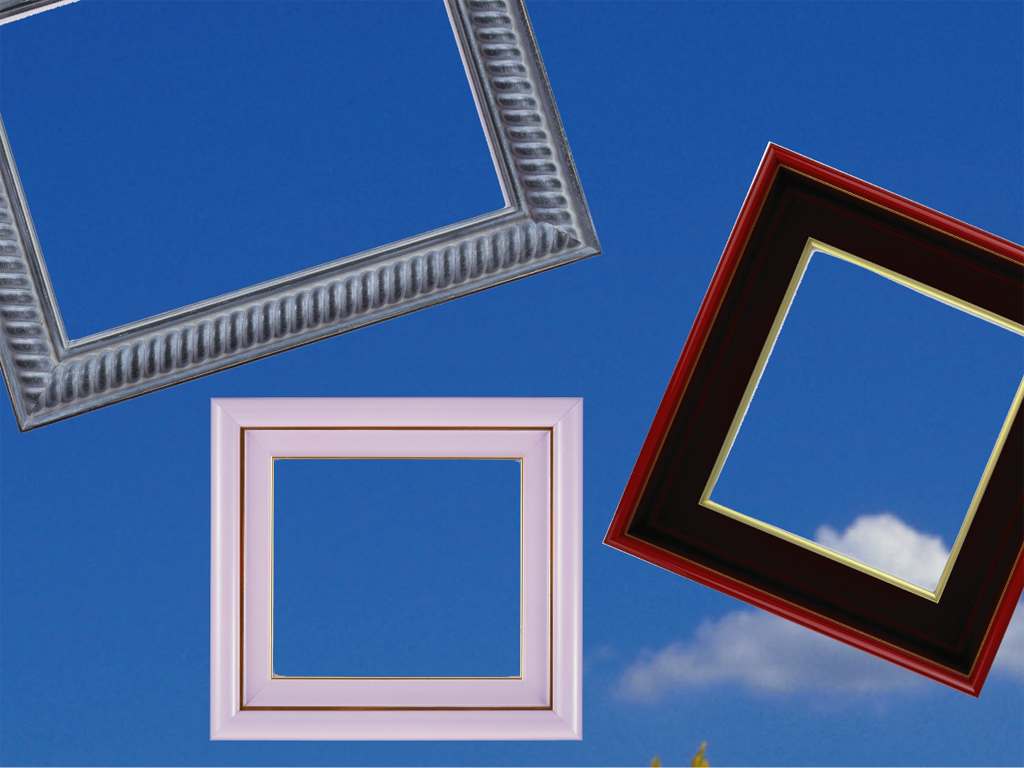麹町九段――中坂
 麹町(こうじまち)九段――中坂(なかざか)は、武蔵鐙(むさしあぶみ)、江戸砂子(えどすなご)、惣鹿子(そうかのこ)等によれば、いや、そんな事はどうでもいい。このあたりこそ、明治時代文芸発程の名地である。かつて文壇の梁山泊(りょうざんぱく)と称えられた硯友社(けんゆうしゃ)、その星座の各員が陣を構え、塞頭(さいとう)高らかに、我楽多文庫(がらくたぶんこ)の旗を飜(ひるがえ)した、編輯所(へんしゅうじょ)があって、心織筆耕の花を咲かせ、綾(あや)なす霞を靉靆(たなび)かせた。
麹町(こうじまち)九段――中坂(なかざか)は、武蔵鐙(むさしあぶみ)、江戸砂子(えどすなご)、惣鹿子(そうかのこ)等によれば、いや、そんな事はどうでもいい。このあたりこそ、明治時代文芸発程の名地である。かつて文壇の梁山泊(りょうざんぱく)と称えられた硯友社(けんゆうしゃ)、その星座の各員が陣を構え、塞頭(さいとう)高らかに、我楽多文庫(がらくたぶんこ)の旗を飜(ひるがえ)した、編輯所(へんしゅうじょ)があって、心織筆耕の花を咲かせ、綾(あや)なす霞を靉靆(たなび)かせた。若手の作者よ、小説家よ!……天晴(あっぱ)れ、と一つ煽(あお)いでやろうと、扇子を片手に、当時文界の老将軍――佐久良(さくら)藩の碩儒(せきじゅ)で、むかし江戸のお留守居と聞けば、武辺、文道、両達の依田(よだ)学海翁が、一(ある)夏土用の日盛(ひざかり)の事……生平(きびら)の揚羽蝶の漆紋に、袴(はかま)着用、大刀がわりの杖を片手に、芝居の意休を一ゆがきして洒然(さっぱり)と灰汁(あく)を抜いたような、白い髯(ひげ)を、爽(さわやか)に扱(しご)きながら、これ、はじめての見参。……
「頼む。」
があいにく玄関も何もない。扇を腰に、がたがたと格子を開けると、汚い二階家の、上も下も、がらんとして、ジイと、ただ、招魂社辺の蝉の声が遠く沁込(しみこ)む、明放しの三間ばかり。人影も見えないのは、演義三国誌常套手段(おきまり)の、城門に敵を詭(あざむ)く計略。そこは先生、武辺者だから、身構えしつつ、土間取附(とっつき)の急な階子段(はしごだん)を屹(きっ)と仰いで、大音に、
「頼もう!」
人の気勢(けはい)もない。
「頼もう。」
途端に奇なる声あり。
「ダカレケダカ、ダカレケダカ。」
その音(おん)、まことに不気味にして、化猫が、抱かれたい、抱かれたい、と天井裏で鳴くように聞える。坂下の酒屋の小僧なら、そのまま腰を抜かす処を、学海先生、杖の手に気を入れて、再び大音に、
「頼む。」
「ダカレケダカ、と云ってるじゃあないか。へん、野暮め。」
「頼もう。」
「そいつも、一つ、タカノコモコ、と願いたいよ。……何しろ、米八(よねはち)、仇吉(あだきち)の声じゃないな。彼女等(きゃつら)には梅柳というのが春(しゅん)だ。夏やせをする質(たち)だから、今頃は出あるかねえ。」
「頼むと申す……」
「何ものだ。」
と、いきなり段の口へ、青天の雷神(かみなり)が倒(の)めったように這身(はいみ)で大きな頭を出したのは、虎の皮でない、木綿越中の素裸(すっぱだか)――ちょっと今時の夫人、令嬢がたのために註しよう――唄に…………どうすりゃ添われる縁じゃやら、じれったいね…… というのがある。――恋は思案のほか――という折紙附の格言がある。よってもって、自から称した、すなわちこれ、自劣亭(じれってい)思案外史である。大学中途の秀才にして、のぼせを下げる三分刈の巨頭は、入道の名に謳(うた)われ、かつは、硯友社の彦左衛門、と自から任じ、人も許して、夜討朝駆に寸分の油断のない、血気盛(ざかり)の早具足なのが、昼寝時の不意討に、蠅叩(はえたたき)もとりあえず、ひたと向合った下土間の白い髯を、あべこべに、炎天九十度の物干から、僧正坊が覗(のぞ)いたか、と驚いた、という話がある。
いざ吉原
 おなじ人が、金三円ばかりなり、我楽多文庫売上の暮近い集金の天保銭……世に当百ときこえた、小判形が集まったのを、引攫(ひっさら)って、目ざす吉原、全盛の北の廓(くるわ)へ討入るのに、錣(しころ)の数ではないけれども、十枚で八銭だから、員数およそ四百枚、袂(たもと)、懐中(ふところ)、こいつは持てない。辻俥(つじぐるま)の蹴込(けこみ)へ、ドンと積んで、山塞(さんさい)の中坂を乗下ろし、三崎町(ちょう)の原を切って、水道橋から壱岐殿坂(いきどのざか)へ、ありゃありゃと、俥夫(くるまや)と矢声を合わせ、切通(きりどおし)あたりになると、社中随一のハイカラで、鼻めがねを掛けている、中(ちゅう)山高、洋服の小説家に、天保銭の翼(はね)が生えた、緡束(さしたば)を両手に、二筋振って、きおいで左右へ捌(さば)いた形は、空を飛んで翔(か)けるがごとし。不忍池(しのばずのいけ)を左に、三枚橋、山下、入谷(いりや)を一のしに、土手へ飛んだ。……当時の事の趣も、ほうけた鼓草(たんぽぽ)のように、散って、残っている。
おなじ人が、金三円ばかりなり、我楽多文庫売上の暮近い集金の天保銭……世に当百ときこえた、小判形が集まったのを、引攫(ひっさら)って、目ざす吉原、全盛の北の廓(くるわ)へ討入るのに、錣(しころ)の数ではないけれども、十枚で八銭だから、員数およそ四百枚、袂(たもと)、懐中(ふところ)、こいつは持てない。辻俥(つじぐるま)の蹴込(けこみ)へ、ドンと積んで、山塞(さんさい)の中坂を乗下ろし、三崎町(ちょう)の原を切って、水道橋から壱岐殿坂(いきどのざか)へ、ありゃありゃと、俥夫(くるまや)と矢声を合わせ、切通(きりどおし)あたりになると、社中随一のハイカラで、鼻めがねを掛けている、中(ちゅう)山高、洋服の小説家に、天保銭の翼(はね)が生えた、緡束(さしたば)を両手に、二筋振って、きおいで左右へ捌(さば)いた形は、空を飛んで翔(か)けるがごとし。不忍池(しのばずのいけ)を左に、三枚橋、山下、入谷(いりや)を一のしに、土手へ飛んだ。……当時の事の趣も、ほうけた鼓草(たんぽぽ)のように、散って、残っている。近頃の新聞の三面、連日に、偸盗(ちゅうとう)、邪淫(じゃいん)、殺傷の記事を読む方々に、こんな事は、話どころか、夢だとも思われまい。時世は移った。……
ところで、天保銭吉原の飛行(ひぎょう)より、時代はずっと新しい。――ここへ点出しようというのは、件(くだん)の中坂下から、飯田町通(どおり)を、三崎町の原へ大斜めに行(ゆ)く場所である。が、あの辺は家々の庭背戸が相応に広く、板塀、裏木戸、生垣の幾曲り、で、根岸の里の雪の卯(う)の花、水の紫陽花(あじさい)の風情はないが、木瓜(ぼけ)、山吹の覗かれる窪地の屋敷町で、そのどこからも、駿河台(するがだい)の濃い樹立の下に、和仏英女学校というのの壁の色が、凩(こがらし)の吹く日も、暖かそうに霞んで見えて、裏表、露地の処々(ところどころ)から、三崎座の女芝居の景気幟(のぼり)が、茜(あかね)、浅黄(あさぎ)、青く、白く、また曇ったり、濁ったり、その日の天気、時々の空の色に、ひらひらと風次第に靡(なび)くが見えたし、場処によると――あすこがもう水道橋――三崎稲荷(いなり)の朱の鳥居が、物干場の草原だの、浅蜊(あさり)、蜆(しじみ)の貝殻の棄てたも交る、空地を通して、その名の岬に立ったように、土手の松に並んで見通された。
出典/青空文庫
薄紅梅・泉鏡花