Home > Today's Book一覧 > 内田百間(百閒)。希代のクソおやじ。
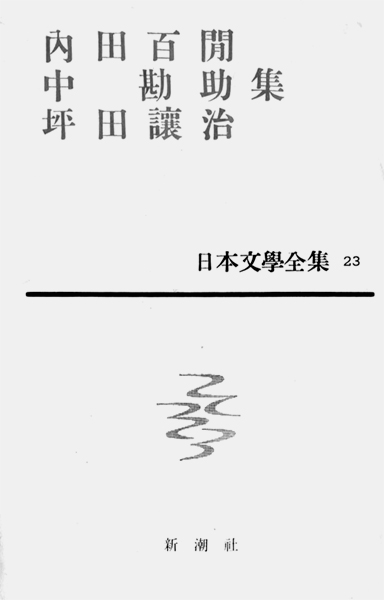
五月、西池袋公園の古書市で、内田百間(百閒)の名が見えたので購入。内田百間の著作と出会ったのは十六歳くらいの頃で、以来、百間と見れば読み漁った。手元に本を置かないので、今も、名前を見れば食指が動く。
『内田百間 中勘助 坪田譲二集』という不思議な名前の並びに、読む前には決してあとがきを見ない主義だけど、どういう意図の編集だろうと、掟を破って覗いてみた。同世代という区切りらしい。随分乱暴だなぁと思いつつ、この三者と、私が最近改めて読んだ泉鏡花やら永井荷風、現在読んでいる岡本綺堂の生まれた年を見てみると、1870年代初めから1890年までに収まっている。敗戦を知る知らないはあるけれど、だいたい明治の草創期に生まれ、大正の関東大震災を経て、大戦へ向かう時代を生きた作家たちだった。
全く意図しなかったけれど、私の目がこの時代の作家に向きがちなのは確かなようだ。そうなると「時代性」というキーワードにも意味があるのかもしれない。
本書に収められている内田百間の著作は、「冥途」「旅順入場式」「昇天」「残月」「サラサーテの盤」「実説草平記(實説艸平記)」「特別阿呆列車」「彼ハ猫デアル」「朝雨」の九編。
「冥途」「昇天」「サラサーテの盤」のようなちょっと不気味で不安な夢の中の出来事のようなスタイルの短編は、百間のお家芸と言えるだろう。さらに「東京日記」のようにナンセンスに突き進んで、ユーモアを奏でる作品も多い。
本書に収録された「旅順入場式」もこうした朦朧体とも言える文体で描かれているが、実は、若い頃にはよく分らない一編だった。しかし、読み返して、これが大正末年に発表されたことが分かると、戦争が拡大する時代の中で百間が感じた理不尽な悲しみが伝わってきた。
独自のスタイルを持つ短編群に対し、私小説めいた「山高帽」などを読むと、狂気ぶっている自己愛の強いインテリといった印象が鼻に突いて、長い小説はあんまり得意では無いという印象を持っていた。しかし、本書に収録された「残月」と「実説草平記」は、なかなかの良作だった。
「残月」は、親友で盲目の琴の師匠・宮城道雄を主人公に、一人称で盲人の心情を創作するという奇想が貫かれている。頑固な主人公は、気遣いの行き届いた女弟子を気にかけるようになるが、震災でその存在を失ってしまう。百間の著作には「ノラや」のように感傷的なものが多いけれども、「残月」は、作家としての視点を保った小説になっている。非常によく知る親友の姿を借り、その心情を描くという体裁を取ったことで、客観性が保たれたのだと思われる。百間は、自分の女の教え子を震災で失った悲しみを「長春香」に記している。それが、この小説のテーマとなったのかもしれない。
「実説草平記」は、漱石門人として先輩である森田草平との交際の回想記。最初、森田は、女好きで我が強いけれど生活力のある頼もしい存在として描かれている。ところが、森田と百間が法政大学の教授として同僚となってから雲行きが怪しくなってくる。円本ブームに乗った森田は羽振りが良くなるが、百間は給料を借金取りに差し押さえられる始末。森田は、百間の金の工面にしばしば答えるけれども、とても快くとはいかない。百間の方でも、鬱憤が積もってくる。さらに森田は、法政大学を割って、百間ら大勢の教授陣を大学から追い出す陣営の筆頭となり、その企みは成功する。以来、百間は森田と疎遠になる。彼は、たまたま森田がその神輿になったのだと言い、恨んでいない風を装うけれども、やはり腹立たしく悲しい出来事であったという嘆息が聞こえてくる。
内田百間の真骨頂は、「特別阿呆列車」に代表される随筆の類だろう。百間という人は、常に借金を重ねながらも、無類の酒好き、食いしん坊、無駄な浪費好き、それでいて執筆は遅い。親しい人間には甘えられるだけ甘え、腹を立てれば執念深い。教え子には大柄かつ小言が多く、自慢話が好きで、見栄っ張りでもある。実務的では全く無く、極めて情緒的な気分屋だ。面識も無いのに言うのは僭越だけれど、希代のクソおやじに違いない。
そんなことは、百間本人も自覚していて、随筆の多くは、自身の性格に対する自虐と開き直りをユーモアの源としている。決して難しい理屈も展開せず、主張もしない。ほとんどは、減らず口であるけれど、その筆は自由闊達で軽妙。読者にお道化てみせるのは、実は人が好きだからに違いない。情緒的な人間故に、孤独や離別の寂しさにも敏感だったのだろう。
一見、とっつき難い先生ではあるけれど、その言動には、人懐っこさや寂しがり屋の顔が透けて見える。だからこそ、多勢の教え子に慕われたし、読者にも愛されるのに違いない。
以前、私は、百間が嘱託時代を過ごした会社に数日足を運ぶ機会があった。その建物の窓から見下ろすと、丸ビルが解体されて、多少の残骸が残る更地になっていた。路上からは、高い囲いに覆われて決して見ることの出来ない光景だった。
「東京日記」に、ある日、百間が丸ビルに用事があって出向くと、昨日まであった丸ビルが消えていたが、翌日には元通りになっていた、という人を食った一編がある。
窓から見下ろした更地は、小説に描かれた丸ビルが消えた跡の風景にそっくりだと思った。予言のために生まれるという人面牛の「件」と、百間の顔が重なった。
※コメントは承認制です。反映に多少お時間を頂きます。